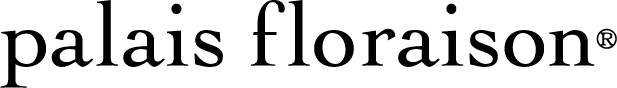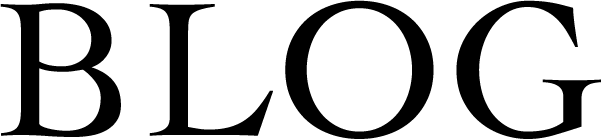水に流せば
普通の家の玄関に見えるその扉を引くと、やはり普通の家の玄関に見えるコンクリートのたたきがあった。
いくつもの靴が並べられているその端に、私は靴を寄せた。
数の合わないスリッパからひとつを拾い上げる母の行動は、すっかりここに慣れた人の、日常の動作だった。
すりガラスの扉を開けると、8畳ほどの部屋があった。
部屋の奥には一段高くなった場所があって、そこに向かって全員が頭を下げている。
母と私も他の人たちと同じように床に座り、手を合わせ、頭を下げた。
建物の裏手には川が流れていた。
川辺に立ち、母が言う。
「あなたには本当はお兄さんがいたのよ」
そう言いながら母は一枚の紙切れを川に流した。
いくらかの沈黙が過ぎたあと
「さ、ラーメンでも食べて帰ろうかな」と母が言った。
ラーメン。
状況に似合わない気の抜けた言葉を聞いて、私は自分の体が緊張していたことに初めて気がついた。
砂利道のザリザリという音を聞きながら、力の入らない足取りで母の後をついていく。
もしこれが映画なら、ドラマティックな展開を期待するシーンなのかもしれない。
でも、この家にはもっとたくさんのドラマがある。
いきなり現れた兄の存在よりも、母にあと幾つの秘密があるのか、そのことが私の足取りを重たくした。
「えりちゃん」
私を呼ぶ母の顔は、太陽の西陽で半分見えない。
「付き合ってくれてありがとうね」
そう言った母の顔には罪悪感など微塵もなく、娘への感謝がふんわりとくっついていた。