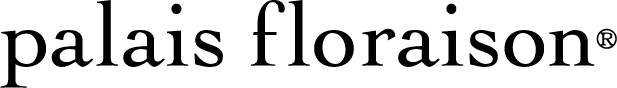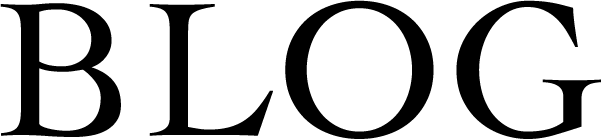バイオリニスト
私の親友はバイオリニストだ。
かつてはオケに在籍していた。今はごくたまに誰かの後ろで演奏をしている。その誰かが大物で、芸能界を知らない私はいつも驚くのだけれど。
彼女には小学生の娘がいて、その娘もバイオリンをしている。
週に1回の習い事ではなく、学校がある日も毎日5時間は練習をして、コンクール前は12時間練習するようなバイオリンだ。
旅行先でも必ず練習をしている。先生についている時間以外は、親子でバイオリンにかかりっきりである。
私たちはしていることこそ違えど、お互いがよく理解できる。
私の娘はかつてバレエをしていた。
3歳から9年間、最後は週8回レッスンを受けるような日々だった。
毎週末県外のレッスンにも連れて行った。朝3時に起きて、帰宅するのは夜中だった。
何者かになるということはそういうこうとで、それをしたところで何者にもなれないことは本人たちが一番よくわかっていた。
それでも辞めないのは、好きだから。好きだったから。
そんなに頑張らなくてもいいんじゃない?
もっとのびのびと育てたら?
それはもう何度も言われた言葉だった。そのたびに娘と顔を見合わせて笑った。
芸事は、本気でやらないのならやらない方がいいとすら思う。
これはビジネスも同じで、中途半端にするくらいなら何もしない方がいい。好きなことをするには、好きではないこともしなくてはならない。好きなことだけをしていたいなら、自分で事業を興すなんてことはしてはいけない。
心に響くバイオリンの音色も、潤沢な事業の利益も、強欲と孤独の先にある。それは簡単に手に入るものではない。
書くことも同じだ。
予定と予定の間の2時間。そうした隙間時間に書けるものではない。
書くためにはたくさんの時間が必要だ。文章の世界に入り込まないと書けない。机に向かっている間、ずっと書き続けられるわけではないし、指が動き始めたらいつ止まるかもわからない。
本は孤独にならないと書けない。楽しく余暇を過ごしながらでは書けないのだ。
今書いているようなnoteなら、隙間時間に書ける。2時間もあれば十分だ。でも本は、私が書いてきたようなタイプの本ですら、1冊書くのに10万字を書く。その10万字は、完璧に辻褄が合わなければならない。最後まで中だるみせずに読み進められるものでなくてはならない。本の原稿を書くのは、ちょっと面白い文章を書けるだけでは無理なのだ。ちょっと面白いのは当然で、体力と根性と孤独な時間がいる。
一人にならないと、自分の声は聞こえない。他人の声は大きく、自分の声は小さい。その小さな声を拾って形にするには、圧倒的な静寂がいるのだ。
作家もバイオリニストも経営者も同じだ。
それを人はストイックと呼ぶのかもしれないが、努力してそうなのではない。そうだから、作家なのだ。そうだから音楽家で、事業家なのだ。
前置きが長くなったが、昨日の続きである。「書くこと」について。
私は20年以上書いてきた。
書いてきたと言っても、自分の体験や感情をぶつけてきただけでお金をいただくようなものではない。
書きはじめた当時、私は大学生だった。女子大でジェンダーのゼミに所属していた。フランス人の彼氏がいるらしいその教授は、それまでに出会った「先生」と呼ばれる人にはない雰囲気を持っていた。
その教授が言った。「情報は、消費する側とされる側に分かれる」
考えたこともない発想だった。18歳の私は心に決めた。私は情報を消費される側になろう。
文章を書き始めたのはそれからだ。どんなに拙い文章であっても、書き続けているとファンはできる。それを大学生のときに体験できたのは、確実に今の須王フローラを作っている。
本を出した3年前、いつか本を出したいと思っていたかと聞かれたが、出したいとか出したくないとかではなく、いつか出すものだと思っていた。
精神世界・自己啓発分野で本を書くとは思っていなかったけれど、商業的にはそれで正解だったと思う。結局私が書きたいのは、現実とファンタジーが曖昧に溶け合った世界なのだということもよくわかった。この世を目に見える側だけで語るのは不可能だ。しかし、それをDNAレベルでわかるのが日本人であり、それを言語化できるのは私に与えられた才能だと思っている。
ただ、残念ながら私には書く才能がなかった。
専業作家になりたいと思ったことはない。それが救いだった。筆だけで食べている日本人作家は両手で数えらえるほどだと沢木耕太郎さんが講演会で言っていた。たしか7人だったと思う。沢木さんもその一人で、ばななさんもそうだ。あとは誰だろう。村上春樹さん・・・と、あとは?
専業作家を目指していないにしても、それにしても才が足らないことには変わりがなくて、書くときは本当に大変な思いをしている。好きか嫌いかと聞かれたらもちろん好きなのだけれど、楽しいか楽しくないかと聞かれたらあんなに苦しいことが楽しいわけがない。私にとっての執筆は、大好きで楽しくないことなのだ。
なのだが、書くということに対して最高の解を得たのでこれを記している。私が20年以上書いてきた理由は、バイオリニストの親友が知っていたのだ。
彼女はたびたび私に「フローラはピアニストなのよ」と言った。
私は、すべての楽器の中でピアノが一番好きで、子どものころからクラシックとともに育ってきた。反抗期だった中学高校時代ですら、短いスカートにルーズソックスをはいてモーツァルトやショパンを聴いていた。オケもいいけれど、一番はピアノソロ。大人になってからハマったガーシュインもピアノ曲だけを聴き込んだ。
ちなみに、自分でピアノは弾けない。弾けらたらいいのになぁと長年思ってきたけれど、一生聴きたいと思えるピアニストを見つけたのでもう自分では弾けなくていい。
なぜ私のことをピアニストだと言ったのかバイオリニストである親友に聞くと、「弾けるか弾けないかではなくて、それだけピアノが好きで、音の一つ一つがわかるのはフローラがピアニストだからよ」と言った。
大好きなピアニストがピアノを弾く映像を観ていたとき、ふとあることに気づいた。このことに気づいたのは、先日日本からドバイに戻る直前のことで、きっと2025年は書くことをがんばりなさいというギフトなのだと思った。
おそらく私はピアノを弾くようにキーボードを打っている。自分の思考とキーを打つスピードが合致して、自分の作り出した世界に没入したときのあの快感。頭の中で音が鳴る、ときに静寂、世界と自分の境界がなくなる、楽しいとか嬉しいとかそういう感情を表すような言葉では表現できない、もっと原始的な快楽に身を委ねて書いている。
あぁそうかとこれに気付いた私は「書ける」と確信した。長く、書いてきた理由もわかった。
楽しいけれど苦しい。でも、やめられない快楽がそこにあったのだ。
人は快がなければ、それをしない。
本当にその通りだと思った。体はいつも正直で、思考や感情は嘘をつく。体が感じている感覚だけを追いかけていけば、人は間違いようがない。
今自分の目の前にあるものすべて、それはたまたまそこにあるのではない。無自覚であっても、それが欲しいと思って手に入れてきたものばかりだ。だから、どんなにそれが気に入らないくても、もっといいものが欲しいと思ったとしても、やはりそれらを大切にすることからしか人生は始まらない。
今目の前にあるものに喜べるのなら、もっと喜んだ方がいい。もっと大袈裟に味わった方がいい。自分の人生を味わうこと、それが生きるということだから。
書くことは生きること。
それに自覚的になれたことが本当に嬉しい。
そんな、書く話。
みなさま、今日も良い一日を。
ごきげんよう。
須王フローラ